くまごろうです。この投稿では午前対策を解説していきます。

この記事では午前対策について、最も効率の良い対策方法や注意点を解説していくよ!
午前Ⅰの対策
くまごろうは午前Ⅰをほとんど受験したことがないため、過去問の比率であったり、効率的な勉強方法などの知識や経験を持ち合わせていません。他の記事を優先したいため、解説を後回しにします。
ただし過去に1度受験した感想としては、
- 応用情報技術者試験できちんと対策をすると、対策が不要の可能性が高い
- 不安なら、あるいは試験当日に余裕が欲しいのなら、午前Ⅰのみの受験して、免除を確保するのもあり
と思っています。
午前Ⅰを受験される方は、一度過去問を確認いただければと思います。
午前Ⅱの特徴
午前Ⅱ試験の特徴としては以下の3つです。
- 共通問題と専門問題に分類できる
- 過去問の比率が高い
- 選択肢はほとんどシャッフルしない
共通問題と専門問題に分類できる
午前Ⅱ試験の問題を分類すると、共通問題と専門問題に分類できます。共通問題はITSSのレベル3で午前Ⅰや応用情報相当、専門問題はITSSのレベル4になります。
比率にすると、例えば手元にある令和2年度のエンベデッドシステムスペシャリスト試験では、共通問題が11問、専門問題が14問でした。
ちなみに出題される共通問題はセキュリティが3問出題されています。IPAはことあるごとに「セキュリティからの出題を強化する」と表明しているので、この傾向は今後も続くと思います。情報処理安全確保支援士試験の取得が、他区分でも役立つお得な資格であることの1例になります。
過去問の比率が高い
午前Ⅱ試験は過去問の比率が高いです。手元にある令和2年度のエンベデッドシステムスペシャリスト試験では、25問中9問が過去に出題されたものでした。
これらを確実に正解させれば、40点程度は取ることができるため、残りの15問で5問正解できれば合格することができます。
これが過去問を暗記するだけで合格圏内に達することができる理由になります。
選択肢はほとんどシャッフルしない
過去問の比率が高いと書きましたが、過去問から出題された場合は、過去の問題がそのまま出題されます。問題文や図解、選択肢ともに完全に同じものです。
まれに選択肢が変化することがあるみたいですが、くまごろうは出会ったことはありません。そんな問題があった場合はどうせ1問です。あきらめていいと思います。
午前Ⅱの対策
対策は王道の対策と邪道の対策の2つを用意しました。
王道の対策
やはり王道の対策は、参考書等で午前問題の勉強を行い、続いて過去問を解いていくことです。
特に午後問題で穴埋め問題が出される試験区分では、この王道の対策を行うことが重要です。基礎知識を身に着ける場合は、試験対策の早い時期(春であれば12月や1月、秋では6月や7月)に行うのが良いと思います。
知識も身につきますし、次の試験にもつながっていきます。余裕があるのであればこちらがおすすめです。
邪道な対策
邪道な対策では参考書での勉強はしません。
まず学習に必要なのは、過去6年分の過去問です。この時に重要なのが解答の選択肢が変更されないことです。
過去問道場に存在する試験区分であれば、そちらで問題ないです。




存在しない区分は・・・どうしましょうか。くまごろうもちょっと困っています。
選択肢を入れ替えてあったり、最新の年度の問題が無かったりするものは使えません。ipaからダウンロードするしかないかなと思います。アプリもマイナー試験はあまり良いのが無かったりするんですよね。
実際の対策方法については、直近の試験から過去6年分の専門問題を暗記してください。目標は問題を見たら解答(ア、イ、ウ、エのいずれか)を即答できるまでです。
最悪、計算問題も解答の暗記だけでOKです。あまりお勧めはしませんが。
くまごろうの場合はスマホで対策をしており、不安な問題をスクリーンショットで保存します。あとはこのスクリーンショットを2~3回確認して暗記しています。
注意点としては、この方法でも合格できる可能性はかなり高いと思いますが、共通問題が得点源にならない方には少しリスクがあることです。この場合、「王道の対策」をされたうえで「邪道の対策」を行ったほうが良いです。
午前Ⅱの注意点
午前Ⅱ問題では注意点が2つあります。
問題が入れ替わるタイミングがあること
シラバスが入れ替わるタイミングで過去問の総入れ替えが発生する場合があります。
例えば平成31年度のシステム監査技術者試験では、システム監査技術者試験で参照されるシステム管理基準とシステム監査基準が変更になったため、問題が大きくわ変わりました。この時に出題されたシステム管理基準とシステム監査基準の新規問題は6問ありました。再出題される過去問が減ることはかなり痛いです。
このような可能性のある試験は、以下のものになります。
- ITサービスマネージャー試験のITIL
- システムアーキテクト試験の共通フレームワーク
- プロジェクトマネージャ試験のPMBOKやプロジェクトマネジメントの手引
- システム監査技術者試験のシステム管理基準とシステム監査基準
試験区分や年度によって、上記に関連する問題の出現率も変わるため、過去問を確認して見極めてください。
これらの変更が予測される場合は参考書等で関連する問題を学習するなど、一般的な対策をおすすめします。
油断すると落ちる
油断すると落ちます。統計的には、例えば令和3年春の安全確保支援士試験では、10%くらいの方が落ちています。
くまごろうも平成30年度のシステムアーキテクト試験で、午前Ⅱを60点で合格したことがあります。自己採点したとき、手が震えました。ちなみにこの試験では午後Ⅰが95点、午後ⅡはAで合格しました。
午前Ⅱで落ちるとそれまでの努力が無駄になります。そうならないようにきちんと対策をしましょう。
午前Ⅱの対策はイメージできたでしょうか。時間があれば「王道の対策」を行ったうえで「邪道の対策」を、時間がなければ「邪道の対策」で乗り切ってください。ただし「邪道の対策」だけではリスクがありますので、その点は考慮してください。
今日の解説はここまでです。
また次回お会いしましょう。それでは!!
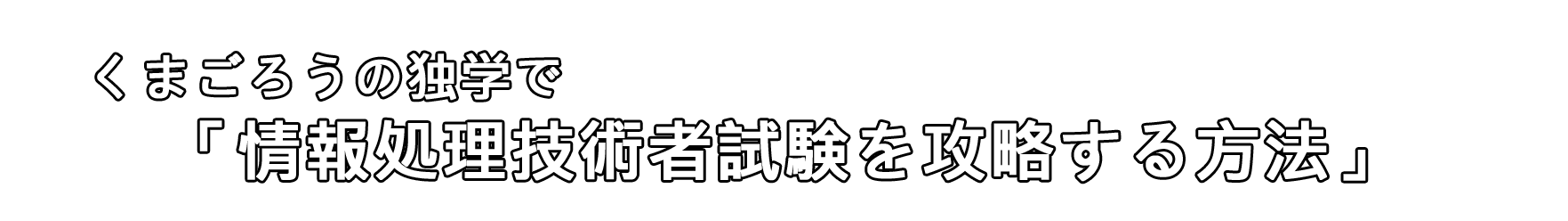



コメント