くまごろうです。この投稿では論文試験に潜んでいる罠について解説します。

この記事では論文試験に潜む罠を解説していきます。正直、結構大きい罠だと思うんですよね。そして罠にはまると合格することはかなり難しいと思います。
何回か挑戦しても合格できない方には、参考になるかと思います。
どんな罠が存在しているのか
罠は2つ存在しています。
1つ目は構造的な問題です。2つ目はあなたが持っている文章の癖に起因します。
この2つの罠をそれぞれを解説していきます。
構造的な問題
IPAは論文試験でどれくらいの論文を書ければ合格できるのか公開されていません。
なのでどれくらいの論文が書ければ合格できるかわからないんです。
参考書の著者達も感覚として理解はできているのでしょうが、詳細についてはわからないのではないでしょうか。
詳細についてわからないので、当然参考書にも「こうしたほうが良いのではないか」「これはしないほうが良いのではないか」としか書かれていません。
構造的な問題だと思うので、順番に解説していきます。
①IPAが公開している情報の問題
記述試験であれば「解答」が公表されているのでわかりやすいのですが、論述試験では「要綱」と「採点基準」、「講評」などしかありません。
要綱について
このブログでは要綱についても触れました。
設問で要求した項目の充足度、論述の具体性、内容の妥当性、論理の一貫性、見識の基づく主張、洞察力・行動力、独創性・先見性、表現力・文章作成能力などを評価の視点として、論述の内容を評価する。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/youkou_ver4_6.pdf
こういった項目が採点に影響することはわかります。わかりますけど、これらの項目がどれくらい影響するかはわからないんですよね。
評価基準について
評価はA~Dの4段階となっており、Aのみが合格です。各評価基準は以下となっています。
| 評価ランク | 内容 | 合否 |
|---|---|---|
| A | 合格水準にある | 合格 |
| B | 合格水準まであと一歩である | 不合格 |
| C | 内容が不十分である 問題文の趣旨から逸脱している | 不合格 |
| D | 内容が著しく不十分である 問題文の趣旨から著しく逸脱している | 不合格 |
このブログでも以下のように書きました。
評価ランク「B」:論文の説得力が不十分。根拠に欠けている。合格まであと一歩。
評価ランク「C」:設問で問われている記述が足りていない。きちんと設問を読み取って、求められている内容を記述しましょう。
評価ランク「D」:文字数に足りていない。おそらく論文を書ききれていないと思われます。
https://www.ipa.kuma-family.net/how-to-study-pm2-1/219/
正直言うとこれで何がわかるんですかね。例えば評価ランク「B」の説得力が不十分。どれくらい不十分だったんでしょうかね。
しかも年度ごとに問題文の難易度によって、合格率を一定の範囲内に収めるために、採点の厳しさが変化しているように思います。
また試験区分間でも、例えばシステムアーキテクト試験とITストラテジスト試験は合格率が同じくらいです。同じくらいの合格率にしようとした場合、受験者の試験経験を考えると、ITストラテジストのほうが採点が厳しくならないとできないと思います。
講評について
講評は平成18年度秋から発表されているものです。
こちらもこのブログで平成24年秋のシステムアーキテクト試験の講評 を紹介しました。
問題文の引用で文字数を費やし、結果的に期待した内容が掛かれていない論述や、問題文に例示した項目と一般論の組み合わせだけで構成された具体性に欠ける論述も見られた。問題文に記載した項目は事例として挙げたものであり、転記を求めているものではないことを理解してほしい。
https://www.jitec.ipa.go.jp
確かに「問題文の引用をたくさんしたらダメなんだ」「具体性に欠ける論述もダメなんだ」というのはわかります。
でもどれくらいやったらダメなのか、やってしまうとどれくらい影響があるのかなどはわからないんですよね。
②参考書の問題
参考書はIPAが公表している情報を受けて記載されます。IPAが明確な基準を公表していないため、参考書は 「こうしたほうが良いのではないか」「これはしないほうが良いのではないか」 しか書けません。
評価に影響する項目は公開されていますが、どれだけ影響するかは公開されていないので当然ですよね。
このような事情から、参考書にも罠が潜んでいます。
論文の合格水準が記載されていない
不確定な情報でしか参考書は書かれていないため、参考書を読んでも合格水準が記載されていません。
正確に言うと、合格論文は掲載されています。そしてその論文が実際の試験で書ければ、95%は合格するでしょう。ちなみに一部怪しい論文を掲載している参考書もあるので、落ちることもあるかもしれません。気を付けてくださいね。
実際に参考書に掲載されている論文と同水準のものを実際の試験で書けるかと言われれば、くまごろうは書けません。
書けないのでもう少しレベルが落ちた、合格水準より少し上の論文を書きたいのですが、参考書に合格水準が記載されているわけではありません。
だから毎回「これくらいなら大丈夫かな?」と独自の基準を見つけ出して対応することになります。
でもこの基準が合格水準以下だったら、一生合格することはないですよね。
これが構造的な罠だと思っています。
サンプル論文のレベルがやたらと高い傾向にある
さらに悪いことにサンプル論文のレベルがやたらと高い傾向にあります。
これがさらに事態を悪化させています。
おそらく100点満点で評価すると90点以上の論文が参考書には掲載されているのではないでしょうか。
これらの論文は以下の特徴を持っています。
- 文字数が3000字以上と実際の試験で書けるか怪しい分量がある
- 論理がしっかりしているし、理由もきちんと記述されている
- 数字や専門用語が適切に使われている
試験対策のプロである参考書の著者が、じっくり時間をかけて作成した論文です。そりゃ素晴らしいです。素晴らしすぎます。
試験当日にそんなレベルの高い論文を誰が書けるんですかね。実際には著者ですら試験では書けないレベルでしょう。試験ではじっくり時間をかけることができませんから。
私たちは「こらくらい書ければ合格できるかな?」っていう現実的な水準を見つけ出して、それを超える論文をコンスタントに書けるように訓練したいんです。
でも90点以上の論文をもとにしてしまうと、理想と現実の論文に差があり過ぎて、独自の合格水準を見つけ出すのは困難です。
現実的な水準が参考書に掲載されていない(掲載されていてもそれは合格水準のかなり上になっている)ので、見つけ出した独自の合格水準が実際の合格水準以下になるリスクが上がっていると思うんですよね。
構造的な問題のまとめ
構造的な問題をまとめると以下になります。
- IPAは明確な合格基準を公開していないため、参考書にも合格水準は記載されていない
- さらに悪いことに、参考書に掲載されている論文は実際の試験では書けないようなハイレベルなものである
- 受験者は現実的な合格水準を見つけ出して、対策を行う必要があるが、かなり難易度が高い
- 見つけ出した現実的な合格水準が実際の合格水準以下の場合、一生試験に合格できない
実際には「設問と論述の対応ができていない」とか、「具体的に対策が書かれていない」、「対策の理由が書かれていない」など、もっと根本的なところで不合格になっている方が多いのではないかと思います。
でも今回解説したような合格水準を見誤って不合格になっている方も一定数いると思っています。
ご自身が準備されている論文のレベルを見直すことも有益ではないでしょうか。
文章の癖 に起因する問題
文章の癖に起因する問題もあると思っています。
文章は、書き手の癖がかなり出てきます。くまごろうの書いているこの文章も、癖があると思います。そして読みにくいと思われている方も多いのではないでしょうか。
文章に問題がある場合に、これを矯正するのはかなり大変です。
みなさんは自分で話している内容を文章にしたことはありますか。絶望するくらい支離滅裂な内容を話していたりしますよ。しかも本人はそのことに気づいていなかったりします。
同様に、これまで何年も書いてきた文章に問題があると気づくことも困難ですし、それを矯正することはもっと難しいです。
なぜなら少なからず自分の能力や常識の否定につながるからです。
また論文には論文の書き方をする必要があります。
例えば新入社員の報告書等を添削することがあるのですが、最初のうちは残念な報告書しか出てきません。これは大学までに求められていた文章と報告書に求められる文章が異なるためです。
報告書は簡潔に事実と自身の見解を分けて書く必要がありますが、これができている新入社員を見たことがありません。
同様に論述試験でも情報処理技術者試験の論文に求められる記述をする必要があるため、初めて論文試験を受験する場合は、情報処理技術者試験の論文を論述する訓練が必要になります。
この論述が身についているかを客観的に見極めるのも難しいんですよね。
対策について
今回取り上げた罠は、個人だけで対応できる範囲を超えていると思っています。①評価基準が明確ではない、②そもそも自分自身で書いた文章を客観的に評価することが難しい、の2点により困難だからです。
なので対策としては、第三者に助言をもらうのが一番効果的です。
以下を検討してみてはいかがでしょうか。
- 通信教育などの添削サービスを受ける
- 論文合格者の助言や添削をお願いしてみる
- 論文合格者の助言が難しければ、管理職など文章を常に書いている人に添削をしてもらう
このブログは「独学で合格」することを目標に情報発信をしています。くまごろうは、誰かのアドバイスを受けたことも、通信教育を受けたこともありません。アドバイスを受けたことがないのは、周りに論文合格者がいなかっただけなんですけどね。
かなり遺憾ではあるのですが、初めて論文試験に挑戦する場合は、通信教育などの添削サービスを受けることは効率的だと思います。
- 論述方法に問題がないのか
- 論述した論文は合格水準に達しているのか
こういった評価を客観的に行うためには、第三者に助言が必要だと思います。「もらえない」あるいは「もらわない」ということは、あなたが書いた論文が「合格水準に達することができない」というリスクがあることを理解しておいてください。
なお通信教育は以下で行っています。参考にしていただければと思います。
大原
TAC

iTEC

論文試験の罠は理解できたでしょうか。今回解説した内容は、くまごろうが論述試験を受けるときにずっと悩んでいた内容です。
くまごろうは幸運にも論述試験を落ちたことはなかった(論述試験を途中退室した試験はノーカンでお願いします)ため、これらの罠にはまることはありませんでした。
もしはまっていたら、数回論述試験を受けた後に受験をやめていたと思います。
当時は漠然と悩んでいました。今客観的に考えると、かなり大きな罠だと思っています。
遺憾ではありますが、通信教育を含めて効率的に対応していただければと思います。
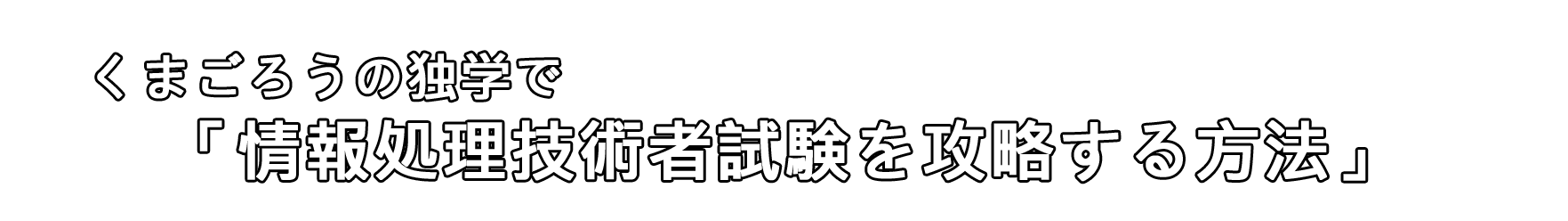



コメント