くまごろうです。この投稿では記述対策を解説していきます。

この記事では記述対策について、最も効率の良い対策方法や注意点を解説していくよ!
記述試験の特徴
記述試験の特徴は、数ページの問題文を読んで最大60字程度で回答する試験です。
もう少し詳しく述べると、問題文に書いてある状況や問題点を読み取り、解答として問題点や解決策を解答する試験になります。
試験は午後Ⅰと午後Ⅱから分かれており、それぞれ以下のような特徴があります。
午後Ⅰ試験の特徴
午後Ⅰ試験の特徴としては、以下になります。
- すべての高度区分に存在している
- 問題文は試験区分にもよりますが4~5ページ
- 試験時間は90分
- 3問中2問を選択して回答する
1問につき45分で解く必要があるため、解答にスピードが求められます。
時間のロスが結構痛い試験で、問題選択に時間をかけたり、選択した問題を変える場合は時間的にかなり劣勢に追い込まれます。
ラスボスである午後Ⅱ試験の受験者を振るい落とすための試験となっています。
午後Ⅱ試験の特徴
午後Ⅱ試験の特徴としては以下となっています。
- 情報処理安全確保支援士、データベーススペシャリスト試験、ネットワークスペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験のみに存在している
- 問題文は試験区分にもよりますが8~12ページ
- 試験時間は120分
- 2問中1問を選択して解答
120分で1問の回答します。くまごろうの経験としても時間が足りなかったという経験はないので、じっくり腰を据えて解く試験です。
午後Ⅰと比較して問題文の設定が複雑で読解力が求められます。難しすぎて泣きながら解いていく試験になります。
試験対策について
試験対策の基本は過去問になります。
受験時と同じように問題文を解き、参考書の解答と答え合わせをします。この時重要なのは解答が一致しているかというよりも、以下に気を付けて採点してください。
- 解答の根拠を見つけ出せているか
- 解答が設問の意図を満たせているか
正直、IPAの回答と完全一致はしません。40字で回答する問題を、IPAの回答は20字だったりします。またIPAの回答は粒度がまちまちで、問題の難易度が高いから回答が甘いものの、仮に問題が簡単だった場合に、この回答だと点数もらえないんじゃないかな?と思ってしまうものもあります。
自己採点に関しては、問題の難易度を勘案して行ってください。問題の難易度の振れ幅があるにもかかわらず合格率が一定であることを考えると、正解となる解答の範囲は難易度も影響していると思われます。問題が簡単であれば、採点は厳しめです。問題が難しければ、採点はゆるめです。
この採点の問題は基準が公開されているわけではなく、例えば問題文全体の難易度を勘案しているのか、設問ごとの難易度を勘案して決めているのかなど不明点は多いです。
誤った問題や解答の根拠を見つけ出せなかった問題は、同じ過ちを繰り返さないように、どのように注意すれば気づけたかなどをノートにまとめて、何度も見直しを行いましょう。
午後Ⅰ対策では時間を図りながら解答してください。その後、40分程度で回答できるのであれば、解答時間を意識する必要はありません。40分以上かかるようであれば、別途解答スピードを速めるための試験対策も必要になります。
時間を早めるための対策としては、以下のようなものがあります。
- 試験区分にもよりますが、最初に問題文を一読しているのであれば、一読をやめる
- 問題文から関連する文章を探すのに時間がかかるのであれば、マーキングを工夫する
- 解答を作るのに時間がかかるのであれば、設問のパターン別テンプレートを作ってしまう
対して午後Ⅱ対策では、時間はあまり意識せず、じっくり解いてみてください。
解答のテクニック
高度試験の記述試験では、問題を解く際のテクニックがいくつかあります。大体どこの参考書にも記載されていますが、おさらいです。
- 接続子やマイナス表現や違和感のある表現はよく注意しよう
- 長文の解答方法はだいたい3パターン
- 設問で問われている内容に注意しよう
- 難しくてもとりあえず埋める
- 難しい問題にあまり時間をかけない
- その他
接続子やマイナス表現や違和感のある表現はよく注意しよう
別解が用意されていることも結構ありますが、情報処理技術者試験も解答は一意になるように問題文を作っています。
解答を一意にするために、問題文には
- 問題文に制約事項を盛り込む
- 解答を導き出すためのヒントを盛り込む
といったものが随所に盛り込まれています。
問題文に制約事項を盛り込む
「問題文に制約事項を盛り込む」であれば、以下のような記述に注意してください。
- 「なお」や「ただし」、「ところで」などの接続子
- 図や表などの注釈
問題文だけであれば上記を入れなくても文章は完結していることが多いです。それにもかかわらず問題文に含まれているということは、含む必要があったから、つまり解答に使われるから含まれていると考えることができます。
解答を導き出すためのヒントを盛り込む
「解答を導き出すためのヒントを盛り込む」であれば、以下のような記述に注意してください。
- それまで学習してきた常識と比べて、明らかにおかしいこと
- 問題のありそうな行動、発言
- そのほか常識と比較しておかしいところ
情報処理技術者試験は該当する試験区分の常識を身に着ける試験です。試験問題に常識では考えられないことが平然と記述されているわけありません。それにもかかわらず記述されているということは、その表現を是正するための処置を解答に書かせるために記述されています。
例えば「ウイルスが検出されたパソコンをそのまま社内LANにつなげたままにした」って記述があれば、「さっさとLANケーブル抜けよ!」って思いますよね。そしてきっと設問には、「A君の行動の何が問題だったでしょうか。」といった設問になっているはずです。解答は当然「さっさとLANケーブルを抜く」ってなるはずです。
これらを読み取ることが解答の前提になります。どのような記述がヒントになって解答が導き出されるかを、過去問の演習を使って身に着けていきましょう。
解答方法はだいたい3パターン
だいたいどのような参考書にも記述されていますが、解答方法は3パターンあります。
- 問題文に解答が書いてあり、それを抜き出すパターン
- 問題文のヒントを使用して解答を記述するパターン
- 一般的な解答を記述するパターン
1.問題文に解答が書いてあり、それを抜き出すパターン
問題文に書いてある解答を「全部」あるいは「一部分」抜き出して解答するパターンの問題です。
例えば「~する理由」を答えさせる問題で、問題文に制約条件が記述されており、その制約条件をそのまま解答させる問題などが該当します。
2.問題文のヒントを使用して解答を記述するパターン
一番多いパターンだと思います。本文中に制約条件やマイナス表現があり、これらを受けて解答させるパターンです。
例えば「社内の共有フォルダにあるフリーソフトのみインストール可能」とする社内ルールがあったとして、その理由を答えさせる問題などが該当します。
ちなみに答えは「偽リンクをクリックしてウィルスに感染するリスクがあるから」などとなります。
3.一般的な解答を記述するパターン
特に問題文にヒントなどがなく、自身の知識で解答する問題です。
例えばエンベデッドシステムスペシャリスト試験で実際に出題された問題ですが、データセンター入館時の手続きが書いてあり、1つ目の作業に「入館申請書類を確認する」ことが書いてありました。この後に行う確認作業を答えさせる問題です。
この問題にはヒントがなく、自分の知識を解答させる問題でした。
ちなみに答えは「身分証明書を提出してもらい、本人確認をする」というものになります。
問題の解答パターンについては、実際に設問を解く際にはあまり意識する必要はないかなと思います。
設問を見て解答のヒントを本文中から探すことになりますが、探すときに本文中に解答になる記述があれば抜き出せばいいですし、ヒントしかないならそこから自分で解答を考えればいいです。何もヒントがなければ、その時に初めて一般的な解答を考えればいいと思います。
設問で問われている内容に注意しよう
これは論文も同じですが、設問で問われている内容に解答することは絶対です。当然ですが設問の意図から外れる回答は、どれだけ素晴らしい解答でも正解ではありません。
問題文からヒントを探すことに一生懸命になるあまり、問題文をきちんと理解できていないことは多いと思います(くまごろうは多いです)。
問題文にもアンダーラインを引いて、設問の要求事項を明確化する、解答を記入した後に設問の要求事項と一致しているかを確認することが重要になります。
難しくてもとりあえず埋める
解答を導き出すのが難しくても、とりあえず解答を埋めましょう。部分点がもらえる可能性が高いです。
そもそも難しい問題は、受験者全員が難しいと感じているはずです。当然その設問の正答率は低くなります。IPAが難易度を考慮して正解の範囲を決めている場合、取りえず埋めた解答でも部分点がもらえる可能性は大いにありますので、解答はとりあえず埋めましょう。
難しい問題にあまり時間をかけない
難しいと感じた問題にあまり時間を割くべきではありません。
仮に1問目が難易度の高い問題だった場合、その問題に時間をかけると時間切れになる可能性があります。
どうせ難易度の高い問題は、受験者皆さん解けていません。また問題文のまだ読んでいない箇所にヒントがある可能性もあります。
とりあえず飛ばして、時間が余るようであれば再度解きましょう。
その他
その他にも以下のようなものに注意して問題を解いていきましょう。
問題文で出てくる固有名詞は確実に解答で使用する
問題文に「関西支社」と固有名詞が書いてあるのに、解答に「関西支店」と書いてしまっては不正解になります。回答で記述する固有名詞は、問題文から(本文だけでなく図や表なども含めて)確実に探して解答するようにしましょう。
問題文で出てくる表現はなるべく解答に利用する
問題文に出てくる表現は、解答でもなるべく利用するようにしましょう。理由としてはIPAの解答を確認すると、解答の大半は問題文の文言を使用していることが多いためです。
問題文の表現を利用することは、利用した文言については文言を考えなくていいというメリットがあります。
デメリットとして問題文から表現を探すのに時間がかかるというものがありますが、関連する記述を探すときに利用する文言は見つけ出せていることが多く、メリットのほうが大きいと考えます。
解答の8割くらいを目安に埋める
解答の8割くらいは埋める気持ちで作成すべきです。IPAの解答を見ると、40文字の設問が、20字で解答していたりとあまりあてはまりせんが、基本的には解答の文字数が多ければ、それだけ細かい解答が期待されているということになります。
IPAの期待には応えるべきです。その目安が8割くらいだと思われます。
解答が短い場合は5W1Hで抜けがないかを考える
文字数と比較して作成した解答が短い場合があります。その場合は記述に何かが足りていない可能性が高いです。
5W1Hを意識して抜けている項目を見つけ出すことは有効です。
設問の選び方
設問の選び方は解答者の特性や試験区分によって変わります。
例えばエンベデッドシステムスペシャリスト試験では、ソフトウェア系問題とハードウェア系問題の2つに大別できますが、ソフトウェア系問題のみ対策した場合は選択肢はありません。
選択肢がある場合の試験区分では、以下のように選択される方が多いのではないでしょうか。
- ある程度問題文を確認して選択する。
- 頭から選択してしまう。例えば午後Ⅰであれば、「問1」と「問2」を選択する。
- 解答量の多い問題を選択する。
- 解答量の少ない問題を選択する。
「ある程度問題文を確認して選択する。」は選択されている方を多いのではないでしょうか。この方法の問題点は、問題を選択するためにどこまで確認をするのか見極めなくてはいけない点です。結局、解きやすそうな問題だと思っても、問題を解いてみて初めて合わないなと思ったりします。どこまで読み込んで問題を選択するかを事前に決めておきましょう。
「頭から選択してしまう。」の場合、問題の難易度の振れ幅があるにもかかわらず合格率が一定であることを考えると、ご自身に合う/合わないを考慮に入れない場合、どの問題を選んでも得点数に大差がないといえるかもしれません。
「解答量の多い問題を選択する。」の場合、たくさんの設問に解答できるように問題自体の難易度が低いかもしれない、という可能性に賭ける戦略です。
「解答量の少ない問題を選択する。」の場合、問題自体は難しいかもしれませんが、1問をじっくり解答するという選択になります。残り時間が少ない場合にも有効かもしれません。
くまごろうの場合は「解答量の多い問題を選択する。」を選択していることが多いです。解答用紙を配られた時点で問題に目星をつけて置き、目星をつけた問題を実際に解いてみて解けそうであればそのまま解いていく、というパターンが多いです。
実際の試験で問題選択に迷わないように、どういう基準で問題選択を行っていくのかは、問題選択の時間を節約するためにも決めておいたほうがよいでしょう。
記述試験の対策はイメージできたでしょうか。試験対策は過去問を解いて、IPAの解答と乖離した理由を考え、次に同じような問題が出たときに、間違えないようにすることがメインの勉強方法になります。
多分これ以外の正解はないと思います。
今日の解説はここまでです。
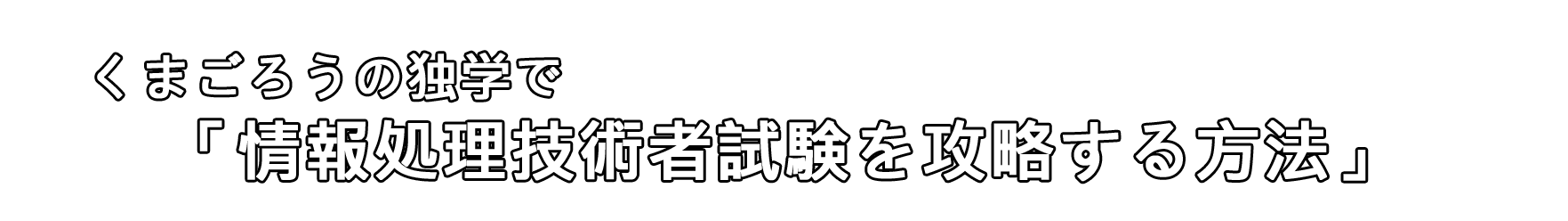



コメント