くまごろうです。この投稿では論文試験の特徴と対策を解説していきます。

この記事では論文試験の特徴と対策について解説します。論文対策②では読み方と骨子の作成について、論文対策③では論文の書き方について、論文対策④は実際の論文を公開していくよ!
論文試験の特徴
論文試験では1ページの問題文を読み込み、最大3600字の論文を記述試験です。
この時重要なのは問題文の意図に沿った自分の経験を論述することで、ご自身の考え方や経験を評価する試験になります。
試験の概要
試験の概要は以下となります。
- システムアーキテクト試験、ITサービスマネージャ試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験、ITストラテジスト試験にのみ存在している
- 問題文は1ページ
- 試験時間は120分
- 2問~3問中1問を選択して論述
- 設問は「ア」「イ」「ウ」が存在し、それぞれに解答する
記述量
「ア」「イ」「ウ」の各設問の論述量は試験区分で異なっています。以下にその文字数を記述します。
| 設問 | システム監査技術者試験 | その他の試験区分 |
|---|---|---|
| ア | 800字以内 | 800字以内 |
| イ | 700字以上1400字以内 | 800字以上1600字以内 |
| ウ | 700字以上1400字以内 | 600字以上1200字以内 |
おそらくシステム監査技術者試験は設問「イ」と「ウ」の重要度は等しくなっています。その他4区分は設問「イ」に比重が置かれているものと思います。
くまごろうとしては、意見の分かれるところではありますが、800字以上の記述を求められているのであれば、タイトルや引用部分を除いた文字数が800字を超えていないと減点になるのではないかと考えています。
たまに問題文を引用しつつ論文を記述すべしという試験対策本があります。それが悪いこととは思いませんが、文字数がぎりぎりの場合は減点の対象になる可能性が高いので注意してください。
例えば平成24年秋のシステムアーキテクト試験の講評では以下のように講評されているので注意してください。
問題文の引用で文字数を費やし、結果的に期待した内容が掛かれていない論述や、問題文に例示した項目と一般論の組み合わせだけで構成された具体性に欠ける論述も見られた。問題文に記載した項目は事例として挙げたものであり、転記を求めているものではないことを理解してほしい。
https://www.jitec.ipa.go.jp
あと文字数のカウントは行単位と言われています。厳密に文字数は数えられていなさそうです。一方で箇条書きを多用した場合「文字数足りない」とみなされる可能性があるので、800字以上の記述を求められているのであれば、文字数ベースで800字を超えるように記述してあげましょう。
評価基準
評価はA~Dの4段階となっており、Aのみが合格です。各評価基準は以下となっています。
| 評価ランク | 内容 | 合否 |
|---|---|---|
| A | 合格水準にある | 合格 |
| B | 合格水準まであと一歩である | 不合格 |
| C | 内容が不十分である 問題文の趣旨から逸脱している | 不合格 |
| D | 内容が著しく不十分である 問題文の趣旨から著しく逸脱している | 不合格 |
各評価ランクは以下のように思っていただければと思います。
評価ランク「B」:論文の説得力が不十分。根拠に欠けている。合格まであと一歩。
評価ランク「C」:設問で問われている記述が足りていない。きちんと設問を読み取って、求められている内容を記述しましょう。
評価ランク「D」:文字数に足りていない。おそらく論文を書ききれていないと思われます。
いろいろ書きましたが基本的には60点取れれば良い試験です。多少文字が汚くても、漢字がミスしていても、文字数が足りなくても、記述が怪しくても、論理が多少おかしくても、説得力が少し薄くても、60点取れれば合格します。
くまごろうは毎回確実に「字が汚い」「漢字ミス」で減点されていると思っています。翌日の「翌」と学習の「習」の判別がつかずに論文記述していた人間なんで。
あと試験対策本で「どこまでやらかしても大丈夫なのか」を検証している本があります。その検証の本質は「どのような行為をすれば一発アウトなのか」を検証しているにすぎません。やらかしちゃって減点されていも合格水準にあったから合格しているだけなので、合格している人がいるからやっても大丈夫と思うのはかなり危ないと考えています。
試験対策について
論文試験の対策は主に以下の2つです。
- 論文を書けるようになること
- 論文のネタを用意すること
1.論文を書けるようになること
論文試験対策の1つ目は論文自体を書けるようになることです。
情報処理技術者試験の論文はどの試験区分でもだいたい同じなので、論文系試験に合格されたことのある方は対策不要かなと思います。
論文を書けるようになるには、以下のハードルがあります。
- 問題を正確に読めるようになること
- 問題から骨子を組み立てられるようになること
- 具体的あるいは説得力のある表現を行えるようになること
- 2時間で2200字から3600字程度を書けるようになること
「2時間で2200字から3600字程度を書けるようになること」については、最初はかなり厳しいと思います。書けるようになるためには、結構な時間と精神力が必要です。
最初はびっくりするほど書けませんからね。
対策については、参考書の論文を参考にしながら、何回か論文を書き続けることです。そうすることによって徐々に論述にかける時間が短くなっていきます。
一般的な対策では最初に「午前Ⅱ」の対策を行い、次に「午後Ⅰ」、最後に「午後Ⅱ」の対策を行っていくかと思います。参考書の記述順序も同じようになっているかと思いますが、論文対策が第一優先です。
くまごろうも最初は4時間くらいかけて論文が完成しませんでした。その後の対策に時間がかかり後悔した記憶があるので、真っ先に論文対策を行うべきです。
残りの項目については、「論文の書き方について」で解説をします。
2.論文のネタを用意すること
論文試験対策の2つ目は、論文のネタを用意することです。論文のネタ集めでは以下のことを行います。
- 過去問を確認する
- テーマの決定と設問アの前半部分の準備
- 演習論文や骨子を作成する
- 合格率の向上を目指して突き詰める
過去問を確認する
論文のネタ集めで真っ先に行うことは「過去問を確認する」ことです。
過去問の確認は、
- どのような内容が問われているのかを確認する
- どのようなテーマであれば論文を網羅できるのかを確認する
この2つを確認するためです。
「どのような内容が問われているのかを確認する」ことで、よく問われているテーマを見極めます。そして自分がその時点で持っている知識や経験の棚卸を行い、知識や経験で対応できるかを確認します。
またよく問われているテーマの演習論文や骨子を準備することで、準備の効率を高めることができます。
「どのようなテーマであれば論文を網羅できるのかを確認する」では、自分が書こうと思っているテーマで対応できるかも確認してください。対応が難しいようであれば、「テーマを変える」「2つめのテーマを作る」などで対応をしていきます。
テーマの決定と設問アの前半部分の準備
過去問の確認で各テーマがある程度決まれば、そのテーマで設問アの前半部分の準備をします。
論文は何らかの問題があり、その問題を論者の知見と経験で解消していくものです。設問「ア」「イ」「ウ」の大まかな役割は、設問「ア」では改善すべき問題点を論述し、設問「イ」では問題点の解消、設問「ウ」では問題点の解消や振り返りを記述していくことが多いです。
このような特性から、設問「ア」では何も問題がないテーマはNGです。
設問「イ」につながっていくように、以下のような問題点を盛り込んでいきましょう
- 予算に制限があり、〇〇人月しかなかった。生産性が維持できないと予算超過する。
- 〇月〇日のリリース厳守が条件であり、遅延が発生するとリリース日が厳守できない
- 〇〇万件の個人情報を保持しており、個人情報が流出すると会社の経営が傾きかねない
- 競争が激化しており、限りある投資額の中から効率的な予算配分をする必要がある
- システムが停止すると発注業務ができなくなり、会社の業務が停止してしまう
このように「リスク」を中心に記述すると良いです。これらを書けるようにテーマを選定してください。
くまごろうの感覚では、
- 個人情報を扱っていて、不正アクセスが発生すると大変なことになるWebの会員システム
- 止まると影響の大きい基幹系システム
- (問題が山済みになっている)オフコンシステム
なんかがおすすめです。正直影響の少ないシステムだと「たいした影響がないなら放置でいいんじゃない?」となってしまいます。
いきなりは思いつかないと思うので、参考書記載の論文や午後Ⅰの問題文を参考に作成してもよいと思います。ただコピーはよくありません。自分が思いつくテーマを参考書を参考にアレンジしてくのが良いと思います。
演習論文や骨子を作成する
過去問の確認で見つけた、良く出題されるテーマの演習論文や骨子を作成していきます。
あるいは参考書に掲載されている過去問を参考に演習論文を作成してもよいと思います。筆者が厳選して必要と思われる過去問を掲載してくれていると思いますので、そこまで外れることはないんじゃないかなと思います。
どれだけ作成するかは人それぞれです。例えば対象試験区分の経験が無い人にとっては、網羅的にたくさん作成する必要がありますし、経験がある人であれば論文で問われている内容を把握するために数本作成するだけでも十分かもしれません。
そのへんはご自身の知識や経験から判断してください。
合格率の向上を目指して突き詰める
ある程度論文の準備が整ったら合格率向上を目指して突き詰めていきます。
論文をリライトする
いくつも演習論文や骨子を書いていくと、初期に作成した演習論文や骨子は修正点が多々見つかると思います。より良い事例や表現を目指してリライトしていきましょう。
実際の試験では、同じ論題が提出されることはありません。しかし準備した演習論文のブロックを組み合わせて論文を記述していくことになるため、リライトしてより良いものにしていくことも合格率向上には有効だと考えます。
様々な論文に対応できることを確認する
再度過去問を確認し、これまでの準備で論文が書けるかを確認します。
確認して論文が書けない場合は演習論文や骨子を作成して準備をしましょう。そうすることで合格率を飛躍的に上げることができます。
論文をある程度覚える
演習論文や骨子を書いてから長い期間が経過すると、過去に書いたものは忘れていきます。定期的に見直しを行い、実際の試験で準備した論文のブロックを引き出せるようにしましょう。
論文の定期的な見直しではなく、さらに一歩進めて、演習論文や骨子をまとめてブロック化しておくのもよいと思います。
「論述の対象とする〇〇の概要」の準備
論文試験では論文の記述以外にも「論述の対象とする〇〇の概要」の質問事項を記入する必要があります。
「名称」であったり、「業種」「規模」「形態」などの質問に答えるものですが、論述するテーマが決まっていれば事前に準備できるので準備を行いましょう。
その際、自身の論述と整合性が取れた形での準備する必要があります。
試験当日は任意のタイミングで記述されることと思いますが、記入タイミングも決めておいたほうがいいと思います。
論文の記述に熱中すると、記入を忘れることがあるからです(経験済み)。それ以降、くまごろうは設問「イ」の後半を記述中に、休憩を兼ねて記述していることにしています。
くまごろうの場合
くまごろうの場合は、「業務経験が無い状態で試験に臨んでいること」「初回合格を目指していること」から、結果的に過剰な準備になっていたと思っています。
最後の論文試験だった「ITサービスマネージャ試験」では、演習論文を5本、骨子を12本作成していました。演習論文は少なめでした。
平均的に演習論文を5~8本、骨子を5~12本くらいが多いのではないかと思います。
テーマについてはどの試験区分もホテル関連で統一しています。これはくまごろうがホテル向けのシステム導入を主に行っているためです。以下を中心に考えていることが多いです。
- 自社予約ページ
- 宿泊予約システム
- 宴会予約システム
「自社予約ページ」は、予約ページという性格上、顧客情報を大量に保有しています。セキュリティ関連の論文は書きやすいです。また予約ができなくなると機会損失が発生すること、一般消費者向けなのでレスポンスが遅い場合も顧客満足度に影響を与えるため、そういった論文を書くときに使っています。
「宿泊予約システム」はホテルの基幹系システムになります。ホテルは予約からチェックイン、チェックアウトという定型業務を大量に行っており、システムありきで業務が行われています。業務フローの改善なんかは効果があるので書きやすいです。また基幹系システムであり、対面業務です。システム停止は大規模障害につながりやすいため、そういった論文を書くときに使用しています。
「宴会予約システム」は、要件定義などでよく使用していました。シティホテルは「宿泊」「レストラン」「宴会」の3部門が主となりますが、「宴会」が社内政治的に一番弱い部門です。要件定義を行う場合は要件の取捨選択をしていくわけですが、予算の制約が多く、すべてをシステム化することはできません。そこで限られた予算の中で、手運用を交えつつ、どのようにご有無フローを構築していくかを書くときに使用していました。
総じて仕事などで扱っているシステムを主テーマに据えたほうが応用力が効くのでお勧めです。
論文試験の対策はイメージできたでしょうか。結局「①論文を書けるようになること」と「②ネタを準備する」ことが論文対策の中心になります。
論文試験初挑戦は「①論文を書けるようになること」の対策が結構大変です。そのため早期から対策を行っていきましょう。
今日の解説はここまでです。次回は読み方と骨子の作成について解説していきます。
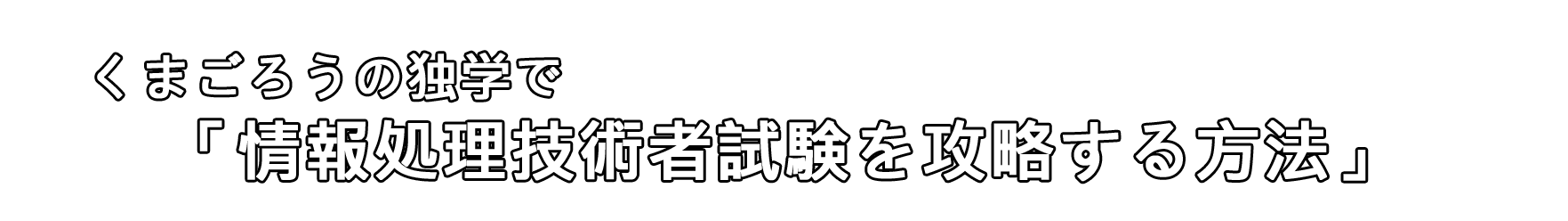



コメント