くまごろうです。この投稿では論文の読み方と骨子の作成方法を解説していきます。

この記事では論文の読み方と骨子の作成方法を解説します。論文対策①では論文試験の特徴と対策を、論文対策③は説得力のある論文とは何か、論文対策④では実際の論文を公開するので、そちらも注目!
ちなみにこの論文は以下で公開しています。よかったら参考にしてください。
はじめに
合格論文を書くには、問題文や設問の条件を正しく読み取って、制限時間内に規定文字以上記述する必要があります。どれだけ経験があったとしても、これらができていなければ合格することはできません。
今回は平成28年のプロジェクトマネージャ試験 午後Ⅱ-問2を例に解説をしていきます。
問題文をダウンロードされる場合は、以下からダウンロードしてください。
問題の読み方
一番重要なのは「問題文を正確に読み取って求められていることを理解する」です。
当たり前と思われるかもしれませんが、問題を正確に読めることが論文試験の第一関門です。
「問題文」と「設問」の関係について
問題は「問題文」と「設問」に分かれています。
「設問」は絶対条件です。設問で指定されている内容の記述が評価の対象となります。例題の「設問ア」であれば、以下を論文に盛り込まなければ評価されません。
- あなたが携わった情報システム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴
- プロジェクトの実行中に察知したプロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候について
「設問」で問われている内容から外れることは致命的です。
例えば本問の講評では以下のように記述されています。
設問が求めたのはプロジェクトの実行中の兆候であったが、プロジェクトの計画中に察知した兆候に関する論述や、すでに対応が必要な、顕在化している問題を兆候として表現している論述も見られた。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
このように「設問」で問われている内容から外れることは致命傷となりますので、くれぐれも注意しましょう。
「問題文」は「設問」の要求事項を論述するうえでのヒントです。さすがに「設問」だけで論述するとイメージがつかみにくいため、イメージしやすいように例示してくれています。
なので「問題文」に記述されている事例については、同じ事例を書くのも問題ないですし、類似の事例でも大丈夫です。
ただし、あまりにもかけ離れた事例を論述するのは、たとえ「設問」に忠実に解答していたとしても、IPAの求めている解答から離れるリスクがあるため、おすすめしません。
章立て
設問を読み込んだ後は章立てを行います。
今回の解説で利用する「平成28年のプロジェクトマネージャ試験 午後Ⅱ-問2」では、設問は以下のようになっています。
設問ア
あなたが携わった情報システム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴、及びプロジェクトの実行中に察知したプロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候について、800字以内で述べよ。
設問イ
設問アで述べた兆候をそのままにした場合に顕在化すると考えたリスクとそのように考えた理由、対応が必要と判断したリスクへの予防処置、及びリスクの顕在化に備えて策定した対応計画について、800字以上1600字以内で具体的に述べよ。
設問ウ
設問イで述べたリスクへの予防処置の実施状況と評価、及び今後の改善点について、600字以上1200字以内で具体的に述べよ。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
設問アであれば「プロジェクトの特徴」「プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候」のよううに特徴をつかんでいるところを抜き出して見出しとします。
同様に設問イでは「顕在化すると考えたリスクとその理由」「対応が必要と判断したリスクへの予防処置」「リスク顕在化に備えてて策定した対応計画について」となります。
設問ウでは「リスクへの予防処置の実施状況と評価」「今後の改善点」となります。
実際には問題用紙にアンダーラインを引いて見出しを決めていることが多いです。
見出しとして設問を抜き出して論文に記述するのは、実際に論文を記述する際に記述がそれないようにするためです。
見出しは該当部分をすべて抜き出しても、多少短く抜き出して論文に記述しても、抜き出した部分は評価の対象とならないので、ご自身の好みで選択してください。
例えば、「対応が必要と判断したリスクへの予防処置」は「リスクへの予防処置」としても問題ありません。くまごとうとしては、記述するのが手間なので、短く抜き出すことが多いです。
設問と問題文の関連付け
見出しが決まれば、次は問題文との関連付けを行います。
設問アの「プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候」では以下が該当します。
プロジェクト実行中に察知する兆候としては、例えば、メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況や、メンバが仕様書の記述に対してわかりにくさを表明している状況などがあげられる。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
設問イの「顕在化すると考えたリスクとその理由」では、上述した記述の続きからが該当します。
これらの兆候をそのままにしておくと、開発生産性が目標に達しないリスクや成果物の品を確保できないリスクなどが顕在化し、プロジェクト目標の達成を阻害する恐れがある。PMは、このようなリスクの顕在化に備えて、察知した兆候の原因を分析するとともに、リスクの発生確率や影響度などのリスク分析を実施する。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
設問イの「対応が必要と判断したリスクへの予防処置」では、さらに上述した記述の続きが該当します。
その結果、リスクへの対応が必要と判断した場合は、リスクを顕在化させないための予防処置を策定し、実施する。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28.html#28haru
このように設問と問題文は関連付けすることができます。見出しとの関連付けもできます。
これをやっておかないと、設問イの「対応が必要と判断したリスクへの予防処置」で、「対応が必要と判断」する基準は「リスク分析の結果」であることを見落としてしまうため、重要です。
注意点としては、
- 基本的には問題文の順序と設問の順序は一致しますが、まれに一致しない
- 設問アの前半(ここでは、「プロジェクトの特徴」)はないことが多い
- 設問ウは記述がない場合や、あっても2文程度で記述されていることが多い
などがあげられます。
論文の設計
問題の読み込みと分析が完了したら、次は骨子の作成を行っていきます。
骨子については、試験対策で骨子を作成される場合は詳細に作りこみます。
しかし実際の試験では時間は貴重なので、箇条書き程度になることが多いです。もっと言えば、演習論文の記述をアレンジして流用できると判断したら「〇〇の演習論文を記述する」しか書いていないことがあります。
骨子は段階的詳細化しながら作成していきます。
第一段階:見出しのみ
第一段階の詳細化は見出しのみです。
1.プロジェクトの特徴とプロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 1-1.プロジェクトの特徴 1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 2.顕在化すると考えたリスクと予防処置及び対応計画について 2-1.顕在化すると考えたリスクとその理由 2-2.予防処置について 2-3.対応計画について 3.予防処置の実施状況と評価及び今後の改善点について 3-1.予防処置の実施状況と評価 3-2.今後の改善点について
第二段階:問題文を埋め込む
第二段階の詳細化は、第一段階の見出しに問題文の記述を組み入れます。
1.プロジェクトの特徴とプロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 1-1.プロジェクトの特徴 1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 兆候の例 ・メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況 ・メンバが仕様書の記述に対してわかりにくさを表明している状況 2.顕在化すると考えたリスクと予防処置及び対応計画について 2-1.顕在化すると考えたリスクとその理由 顕在化するリスクの例 ・開発生産性が目標に達しないリスク ・成果物の品質を確保できないリスク 理由 ・察知した兆候の原因分析 ・リスク分析(リスクの発生確率や影響度) 2-2.予防処置について ・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ 2-3.対応計画について ・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ 3.予防処置の実施状況と評価及び今後の改善点について 3-1.予防処置の実施状況と評価 3-2.今後の改善点について
第三段階:経験や知識を入れる
第三段階の詳細化は、第二段階のに自身の経験や知識を加えていきます。
1.プロジェクトの特徴とプロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候
1-1.プロジェクトの特徴
【論述の対象】
・オフコンで稼働している宴会管理ステムの再構築プロジェクト
【特徴】
・再構築であるため予算に余裕がない
・実績のない社内標準化予定のフレームワークの採用。経験者なし。
→製造初期において開発生産性が低い
1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候
兆候の例
・メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況
・メンバが仕様書の記述に対してわかりにくさを表明している状況
【リスク】
・開発生産性が回復せずに予算超過すること
→EVMを用いて進捗管理を行う
【兆候】
・ACやPVを確認すると想定通り回復しているが、ベテラン要員だけで残業の発生が目立つ
→リスクにつながる兆候ではないかと考える
2.顕在化すると考えたリスクと予防処置及び対応計画について
2-1.顕在化すると考えたリスクとその理由
顕在化するリスクの例
・開発生産性が目標に達しないリスク
・成果物の品質を確保できないリスク
理由
・察知した兆候の原因分析
・リスク分析(リスクの発生確率や影響度)
【顕在化すると考えたリスク】
・残業が増加すると開発生産性が目標に達しない
→予算超過するリスク
【原因分析】
・PLにヒアリングをして確認
→フレームワークの部品の調整ノウハウがなく時間がかかっている
【リスク分析】
・一般メンバーも難易度の高いプログラム開発に着手する予定だが、
このまま放置すると予算超過すると考えられた。
2-2.予防処置について
・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ
【予防処置】
・フレームワーク製造元部署から要員を派遣してもらい以下を検討する
①集合教育
②OJT
→OJTに。基礎的な知識の共有ではなく、詳細なノウハウの共有だから。
またベテランに対して行い、文章化、チーム内共有する。
2-3.対応計画について
・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ
【対応計画】
・生産性が目標に達しない場合に実施。以下を検討
①OJTの延長
②製造要員の派遣又は開発の外部委託
→ノウハウのたまらない①はやりたくない
両方対応計画として持っておくけど、①で改善できる見込みがなければ②を実施
3.予防処置の実施状況と評価及び今後の改善点について
3-1.予防処置の実施状況と評価
【実施状況】
・OJTを行い文章で共有化した。生産性は回復した。一般の要員も生産性低下はなかった
【評価】
・生産性が回復したことから成功
3-2.今後の改善点について
【改善点】
・製造元の部署からの要員派遣は、費用の関係からOJTに限定をして依頼をした。
しかしその後も高頻度で問い合わせを行った
→製造元部署からクレーム。協議の結果、ノウハウ全社公開を条件に費用折半。
自部署分はプロジェクト予備費より支出した。
→予見できていたので、事前に協議していたほうがスムーズだったのが改善点
骨子の作成は以上です。実際の論文については以下で公開します。
その他考慮点
見出しのつけ方
見出しのつけ方は「見出し」を軸につけるのか、説明したい「事例」などを軸にしてつけていくのかは一考する必要があります。
よく設問イでは、「課題」と「対応策」の記述を求めれることがあります。その場合、課題を2つほど記述し、2つの課題にたいして対応策を記述します。
「見出し」を軸にして記述する場合、以下のようになります。
2.課題と対応策 2-1.課題 課題Aの記述 課題Bの記述 2-2.対応策 課題Aに対する対応策の記述 課題Bに対する対応策の記述
一般的に参考書で紹介されているのは上記のような書き方ですが、この場合「課題Aの記述」を読んで「課題Aに対する対応策の記述」を読んでいくことになります。そうすると文章量が多くなるにつれて読みにくくなります。
「事例」を軸にして記述する場合、以下のようになります。
2.課題と対応策 2-1.事例Aについて 〇課題について 事例Aの課題を記述 〇対応策について 事例Aの対応策の記述 2-2.事例Bについて 〇課題について 事例Bの課題を記述 〇対応策について 事例Bの対応策の記述
こちらのほうが上から下に読めるため、文章としては自然な流れであると考えます。
事例を2~3個記述する場合は、少し考慮してみてもいいのではないかと考えています。
設問「ア」と「イ」、「ウ」の関連付けを考える
今回例題としている論題でも同様ですが、設問「ア」と「イ」、「ウ」の関連付けに注意しましょう。
今回の例題では、設問「イ」は設問「ア」の後半部分の「プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候」を受けて作られています。
同様に設問「ウ」も設問「イ」の「予防処置」を受けて、「予防処置の実施状況と評価」を受けています。
設問「ウ」の「今後の改善点」についても「予防処置」の改善点についての記述になります
このように各設問は、それ以前の論述を受けて作られているため、各設問の関連性は注意を払う必要があります。
設問イで書いた事例は微妙に失敗させる
設問「ウ」では、設問「イ」で記述した内容の評価や改善点について記述させる問題が多いです。
今回の例題でも設問「ウ」では設問「イ」の改善点を記述する問題ですが、設問「イ」の対応が完璧だと設問「ウ」での改善点を記述できなくなります。
設問を確認したうえで、設問「ウ」で改善点を問われる場合は、設問「イ」で微妙に失敗させる、落ちをを準備しておきましょう。
論文の読み方と骨子の作成はイメージできたでしょうか。論文は「忠実に設問と問題に解答できるのか」が重要であり、骨子の作成でも同様です。
「忠実に設問と問題に解答できるのか」を考えずに自分の経験を書いていくと試験に合格できません。それは評価の対象とは関係ないことを論述しているからです。
このへんも論文試験初挑戦の方が陥りやすい罠だと思っています。
今日の解説はここまでです。次回は「説得力のある論文とは何か」や「その他注意事項」などについて解説していきます。
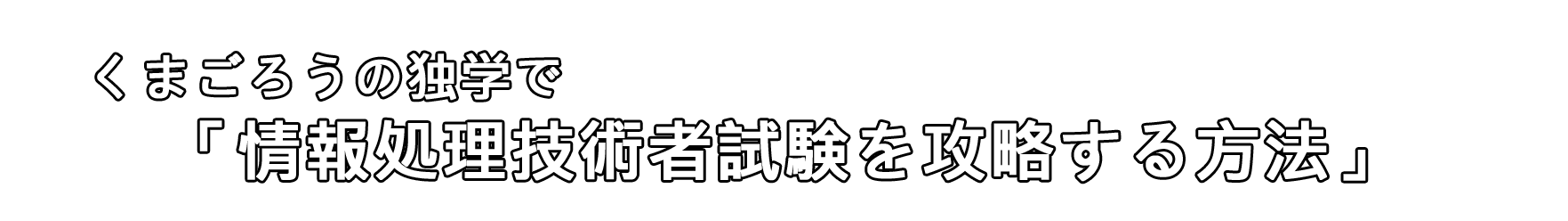





コメント