くまごろうです。この投稿では説得力のある論文の書き方について解説していきます。

この記事では説得力のある問題の書き方を解説します。論文対策①では論文試験の特徴と対策を、論文対策③は説得力のある論文とは何か、論文対策④では試験当日について公開するので、そちらも注目!
ちなみにこの論文は以下で公開しています。よかったら参考にしてください。
論文試験の評価ポイント
説得力のある論文を書くには、論文試験の評価ポイントを知ることが必要です。
IPAの試験要綱において「午後Ⅱ(論述式)試験の評価方法について」として、以下のように記述されています。
設問で要求した項目の充足度、論述の具体性、内容の妥当性、論理の一貫性、見識の基づく主張、洞察力・行動力、独創性・先見性、表現力・文章作成能力などを評価の視点として、論述の内容を評価する。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/youkou_ver4_6.pdf
これらの評価ポイントを満たす論文が合格論文となります。
要約すると以下になると思います。
- 設問で要求された内容を一貫性をもって忠実に書くこと
- 論文を具体的に書くこと
- 論文で記述する対策等の理由を記述すること
- 論文としての表現・文章の作成を行うこと
「設問で要求された内容を一貫性をもって忠実に書くこと」は、「設問で要求した項目の充足度」「論理の一貫性」なんかが該当します。これは「資格の勉強方法 ~論文対策② 読み方と骨子の作成編~」で解説した問題の読み方と骨子の作成が該当します。
詳細は以下の記事を参照してください。
「論文を具体的に書くこと」は、論文は「あなたの経験と考えに基づいて」記述するものですから、抽象的に書いてしまうとあなたの経験や考えを表現できません。
「対策等の理由を記述すること」は「見識の基づく主張」「洞察力・行動力」「独創性・先見性」を表現するために重要です。
「論文としての表現・文章の作成を行うこと」は論文を書いているのですから、当然守るべき論文作成のルールがあります。当然守るべきです。
「設問で要求された内容を一貫性をもって忠実に書くこと」はすでに解説しているため、それ以外を解説をしていきます。
論文を具体的に書くこと
論文を具体的に書くために「具体的に書くための文字数」「具体的に書くために気を付けること」「具体的に書くための方法」をそれぞれ解説します。
具体的に書くための文字数
論文を具体的に書くためにはある程度の文字数が必要になります。くまごろうとしては、「見出し」や「問題文の引用」を除いた独自の記述が、設問の最低文字数以上であることを推奨します。
例えば設問で「800字以上1600字以下で記述」を求められているのであれば、「見出し」や「問題文の引用」を除いて「800字以上」記述することを推奨します。
目安としては、設問イで多い「800字以上1600字以下で論述」であれば「1200字」程度、設問ウで多い「600字以上1200字以下で論述」であれば「800字」程度ではないでしょうか。
〇文字数の注意点
参考書で記載されているサンプル論文は、文字数が多すぎです。3000字を超える論文、特に「3200字」とか「3400字」とかの論文を実際の試験で記述するのはすごくしんどいです。
くまごろうもシステム監査技術者試験で、論文をきれいにまとめることができず、3400字程度の論文を書いたことがあります。その試験の最後は時間が足りずに殴り書きになっていました。
確かに90点以上のハイレベルな論文を記述するためには、「3200字」とか「3400字」とかの記述は必要かもしれませんが、実際の試験に即しているとは思えません。
多すぎる文字数は論文を書ききれないというリスクにつながりますので、文字数は十分に注意しましょう。
具体的に書くために気を付けること
具体的に論文を書くためには何が必要でしょうか。ここでは「資格の勉強方法 ~論文対策② 読み方と骨子の作成編~」の骨子を使って、以下を解説していきます。
- 詳しく説明することを心掛ける
- 知らない人に伝えることを心掛ける
- 5W1Hを意識する
- 数字を使用する
詳しく説明することを心掛ける
論文を具体的に書いてくうえで一番重要なことは「詳しく説明する」ことを意識することです。
例えば
1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 兆候の例 ・メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況 ・メンバが仕様書の記述に対してわかりにくさを表明している状況 【リスク】 ・開発生産性が回復せずに予算超過すること →EVMを用いて進捗管理を行う
「開発生産性が回復せずに予算超過する」では具体的ではありません。何に対する開発生産性なのかを詳しく説明する必要があります。
製造工程において製造初期段階の生産性が想定通りに回復せず、結果として予算超過が発生する
のようになります。
また「EVMを用いて進捗管理を行う」も具体的ではありません。これも
製造初期段階ではプログラム単位にEVMを用いて、週次で進捗確認を行うことを計画した
のように詳しく記述していく必要があります。
知らない人に伝えることを心掛ける
通常、私たちは相手がある程度の知識を持っていることが前提で会話を行います。しかし論文試験においては、採点者は論述されるプロジェクトを知りません。
共通認識がないことを前提として論述を行いましょう。
例えば骨子では
2-3.対応計画について ・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ 【対応計画】 ・生産性が目標に達しない場合に実施。以下を検討 ①OJTの延長 ②製造要員の派遣又は開発の外部委託 →ノウハウのたまらない①はやりたくない 両方対応計画として持っておくけど、①で改善できる見込みがなければ②を実施
「ノウハウのたまらない①はやりたくない」のように書きました。
背景には
自部署でも今回の開発フレームワークを利用した案件が増えることが想定される
という共通認識があれば伝わりますが、採点者には伝わりませんので、その背景は説明すべきです。
また使っていい専門用語は情報処理技術者試験で出題されている用語のみだと思ってください。
マイナーなフレームワーク名とか言われても誰もわからないです。
業界用語も使うべきではありません。例えば「ADR」とか言われても「何やねん」って思いますよね。このような用語も使ってはいけません。
ちなみに「ADR」はホテル用語で「平均客室単価」になります。ホテルの室料売り上げを稼働客室数で割って求める値で、KPIの1つです。
ニュアンスにも注意が必要です。
極端な例ですが「アサインする」という用語は、IT業界では人や物などを「手配する」という意味で使います。しかしホテル用語では「予約に対して客室をアサインする」というように、予約に対して客室を割り当てる意味で使います。
このようにニュアンスが異なっている場合がありますので、この辺りも注意して使いましょう。
5W1Hを意識する
実際に具体的に書くには「5W1H」を意識して論述しましょう。
例えば骨子では【リスク】の項目で
1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候 兆候の例 ・メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況 ・メンバが仕様書の記述に対してわかりにくさを表明している状況 【リスク】 ・開発生産性が回復せずに予算超過すること →EVMを用いて進捗管理を行う
「EVMを用いて進捗管理を行う」と書きました。これを具体的に表現するために、5W1Hを用いて具体化していきます。
When→製造初段階で
Who→私が
What→プログラム単位での進捗管理を
Why→回復しないとリスクが大きいので
How→週次で確認する
今回の例では「Where」とかありません。論文では明らかなことは記述しなくてもよいので「Who」は記述する必要ありません。
このように5W1Hを意識して論文を記述するようにしましょう。
数字を使う
数字を論文に盛り込むことは、具体的な論文にするために有効です。
また数字を使用する場合は、パーセントより具体的な数字のほうが、より具体性が増します。
例えば運営費用を「30%削減する」よりも「1.5億円削減する」のほうが書くための難易度も上がり専門性をアピールできます。より具体的に見えます。
今回骨子で使用したテーマは「今は問題ないが、問題が発生しそうな兆候が表れてきたから対応しましょう」というものです。進捗などが遅れているわけではないので、どれくらい進捗などが遅れているといった差を書きにくく、数字を使いにくいためあまり使っていません。
それでも
1-2.プロジェクト目標の達成を阻害するリスクにつながる兆候
兆候の例
・メンバの稼働時間が計画以上に増加している状況
に対して、「製造開始4週間後、ACやPVを確認すると計画通りに開発生産性が回復していることが分かった。しかしそのころから一部のベテラン要員で週平均3時間の残業をするようになっていた」のように、できる限り数字を出すようにしています。
数字で表現できるものはたくさんあります。工期、工数、予算、実績、プロジェクト人数、開発生産性、ステップ数、画面数、帳票数、テスト項目数、バグ摘出数、バグ密度・・・
一般的な指標から専門的な指標まで様々なものがあります。出せる数字はできるだけ出すように努力してみましょう。
対策等の理由を記述すること
論文では「見識の基づく主張」「洞察力・行動力」「独創性・先見性」を表現する必要があるため、実施する対策などは必ず理由を説明する必要があります。
なぜならば「〇〇の対策を実施した」だけでは、仮にその対策が妥当であっても、あなたの考えは採点者に伝えることができず、採点者が評価できないからです。
あなたの考え、洞察力、独創性などを表現するために、必ず実施する対策には理由を説明しましょう。
理由をつける場合は、いくつも方法があります。
- A案とB案を検討した結果、A案を採用した。なぜならば・・・
- 〇〇を実施した。なぜならば・・・
- 〇〇の基準に則ってランク付けを行い、上位のものを実施した。なぜならば・・・
要は、あなたの行動には必ず理由があるはずなので、それさえ表現できていれば何でもいいです。
例えば案を比較する骨子を書きました。
2-3.対応計画について ・2-1で予防処置が必要だと判断した場合のみ 【対応計画】 ・生産性が目標に達しない場合に実施。以下を検討 ①OJTの延長 ②製造要員の派遣又は開発の外部委託 →ノウハウのたまらない①はやりたくない 両方対応計画として持っておくけど、①で改善できる見込みがなければ②を実施
実際に論述を行うと以下のようになります。
「①OJT期間を延長する、②フレームワーク開発元の部署に対して開発要員を派遣してもらう、又は高難易度のプログラムの製造を委託することを考えた。今後もこの開発フレームワークを利用して開発する案件が増えることを考えると、自部署として②のようなノウハウが部署に蓄積しない方法は取りたくない。そこで予防処置の効果によってOJTで対応できる場合は①を、期間を延長しても対処できない場合は②を行うことにした。」
というように、「検討した案を書き、対応計画として両案を保持したうえで、状況に応じて使い分ける」という私の考えを表明しています。
理由を書くことは、ほかにも論文を具体化する効果も持ち合わせているので、理由も意識して論述していきましょう。
論文としての表現・文章の作成を行うこと
論述試験ですので、当然「論文としての表現・文章の作成を行うこと」も重要です。
論文を記述するうえでは以下に気をつけましょう。
- 丁寧な文字を心掛ける
- 誤字・脱字に気を付ける
- である調にする
- 書き言葉を心掛ける
- 禁則処理を守る
「丁寧な文字を心掛ける」「誤字脱字に気を付ける」これは心掛けるべきです。採点者は人ですので、自が乱れていたり、誤字脱字が多い場合、確実に心象はよくありません。減点される可能性がありますので、心掛けましょう。
ただ、くまごろうの字の汚さと誤字・脱字の多さを考えると、採点者はしんどくても読んでくれます。減点もそんなに多くはないと考えています。実際のところは不明なんですけどね。
「である調にする」「書き言葉を心掛ける」は、論文は基本的には「である調」で「書き言葉」で書かれているものが多いので、この2つに準拠して損はないです。「書き言葉を心掛ける」とかは、多少怪しいところがあっても減点されるとも思えないので、そんなに神経質になる必要はないと思います。
あくまでも本質は「あなたの経験と考えを表現すること」ですからね。
「禁則処理を守る」も遵守すべきです。「禁則処理」は文字の汚さや誤字脱字と同様に明確なので、減点される可能性があります。
説得力ある論文の書き方はイメージできたでしょうか。論文は「あなたの経験と考えを表現するもの」であり、これらを表現するにためには「具体的」で、あなたが記述した対策の「理由」を記述することが重要です。
私たちはいつもある程度事情を知っている人とコミュニケーションを取っています。しかし採点者はそうではありません。新入社員に説明するくらいの気持ちで論文を書いてもいいかもしれません。
今日の解説はここまでです。次回は「試験当日」について解説していきます。
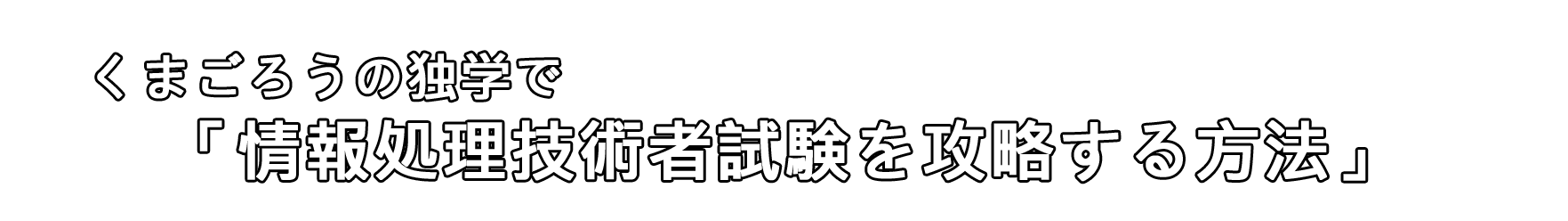





コメント