くまごろうです。この投稿では試験当日について解説していきます。

この記事では試験当日について、設問の選び方などを解説します。論文対策①では論文試験の特徴と対策を、論文対策②で設問の読み方と骨子の作成を、論文対策③は説得力のある論文とは何かを解説しています。そちらも注目!
試験開始前
みなさんは試験開始前に何をされますか。くまごろうは漢字の暗記と論文の骨子など、事前に準備したまとめを確認していることが多いです。
試験当日の時間は貴重です。当日確認するためのメモなどは事前に準備しておくことが重要でしょう。
当日の設問の選び方
試験開始直後に行うのは設問選びです。これもどのような基準で選んでいくかを試験勉強を通して決めておく必要があります。
ではどのように設問を選ぶのが最善でしょうか。
それは「設問を読んでみて書けそうなものを書く」これに尽きます。
すべての問題を読んでみても時間はそんなにかからないので、全問読んでから判断しています。
「書けそうだな」と思った場合
「書けそうだな」と思えれば論文の見出しを作成し、各見出し単位で書けるかどうかを判定します。
こういった場合は、実際に準備した演習論文や骨子と類似している場合で、それらを組み合わせれば論述できる見通しがあると思います。
こういった問題に出会えたらラッキーですね。
設問を決めたら、メモ程度に骨子を作成して、実際に論述をしていきましょう。
「微妙だな」と思った場合
一番多いのは「微妙だな」と思う場合です。くまごろうは7割くらいは微妙だと思って書いています。
その時は問題文の事例を参考に、頑張ればかけそうな設問を探していきます。
比較的書きやすそうな問題を選んだら、あとは骨子を具体的に作成して論文設計を行いましょう。論文設計の目標は「事例」と「対策」くらいは記述しておきたいところです。
「無理じゃないか」と思った場合
「無理じゃないか」と思った場合は、一番書きやすそうな問題を選びましょう。
そして制限時間を決めて骨子を作成していきます。20分と決めているのなら20分間は骨子を作成してアイディアを出しましょう。
制限時間が来た場合は、論述しているとアイディアが浮かんでくる場合があるので、たとえ骨子が未完成だったとしても論述していきます。
実際に平成31年度のシステム監査技術者試験で全くアイディアが浮かばず、骨子未完成で論述したことがあります。設問アを論述中に「オンライン教育で行けるのではないか?」と思いつき、普段は会社で「オンライン教育なんて無意味だ」と思っているにも関わらず、オンライン教育で論文を書き上げ合格しました。
ちなみにこの論述試験では「オンライン教育」という単語を思い出せず、「インターネット教育」という造語を創造して合格しています。
無理だと思った場合でも、時間切れになるまではアイディアを思いついて合格できる可能性があるため、最善を尽くしましょう。
論文の記述
設問選択後は問題を分析して骨子を作成し、論文を記述していきます。
これらについては以下を参照してください。
概要(アンケート)の解答
試験時間中に概要(アンケート)の解答を行います。
これは評価の対象となっています。その証拠に平成30年度のプロジェクトマネージャ試験の採点講評にて以下のような講評がされています。
”論述の対象とするプロジェクトの概要”で記入項目に不整合がある、又はプロジェクトにおける立場・役割や担当した工程、期間が論述内容と整合しないものが見られた。これらは論述の一部であり、評価の対象となるので適切に記述してほしい。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2018h30.html#30haru
よって概要(アンケート)もきちんと準備をしておく必要があります。
準備するタイミング
概要(アンケート) は、試験勉強で設問アの前半を考える時にセットで作りこみます。
これは設問アの前半の作りこむ過程で、「名称」「対象とする企業や機関の種類や規模、業務の領域」「システムの構成」「対象システムの利用規模」「あなたの立場やチーム、期間」など、概要(アンケート)で記述するような情報を想定して作りこんでいるはずだからです。
それ以外の記述内容は、微調整はあるにしても、実際の試験で大きく変わることはないと思われます。
注意すること
注意することとしては先ほど引用した通り、論述内容と整合性が取れていることです。
選択肢に「わからない」があります。親切そうに見えますがこれは罠です。選んではいけません。
後半の「あなたの立場」については、特に整合性に注意してください。システムの形態や利用者人数などは多少おかしくてもバレませんが、「あなたの立場」については論述内容と密接にかかわってきますので、注意が必要です。
特に「あなたの役割」については、論述内容と整合性を取ってください。基本的に論文試験はマネジメントする側の試験となります。論述内容もマネージャー等の視点から行っていると思われますので、「あなたの役割」についてもマネージャー等を選択する必要があります。
記入タイミング
記入タイミングは試験時間内であればいつでも良いと思われますが、くまごろうは設問イを半分くらい論述したタイミングで、休憩を兼ねて書いていることが多いです。
ただし論述に熱中して記入することを忘れる場合や、論文が書ききれるか怪しい場合に概要(アンケート)が未記入だと焦りが生まれる場合がありますので、中盤当たりまでに書いておくのが良いかとは思います。
見直し
論述が完了すれば見直しをすると思います。
みなさんはどのように見直しをされていますか?くまごろうの見直しは読めない文字を治すところから始まります。


え、そんなの時間の無駄じゃないの?
思いますよね。そう、時間の無駄なんです。無駄なんですが読める文字が書けないので、仕方がないのです。
見直しは主に以下を行っていきます。
- 誤字・脱字の確認
- 単語などに誤りがないかの確認
- 論述が破綻していないかの確認
- 問題が選択されているか、受験番号や生年月日が抜けていないかの確認
- 概要(アンケート)と論文に破綻がないのかの確認
問題は「 論述が破綻していないかの確認」を行って、修正可能なレベルの場合にどのように直していくかです。
一番直しやすいのは修正する論述を打ち消し線で消し、論述するマス目の上に新たに記入することです。これが許されるのかは判明していません。
「この方法で訂正しても合格した」という話は聞いたことがあります。しかしもともとの論文の評価が高くて、減点されているけど合格点を超えていたから合格しただけかもしれません。
打ち消し線で訂正する方法はリスクがあるので、くまごろうはやったことがないんですよね。
結局、訂正したい論述を消しゴムで消し、マス目に合うように文章を考えています。
番外編:試験終了後
試験終了後はだいたい死んでいます。ベンチで死んだ魚の目をしていることが多いです。
あとは5chを見て帰宅していることが多いですね。
帰宅後は午前Ⅱの採点をしています。
本当であれば次回に向けて、解答などをまとめておくのが良いと思うですが、気力が残っていないのでやったことがないです。
「設問の選び方」と「概要(アンケート)」の書き方、「見直し」については参考になったでしょうか。
午後試験の「設問」は、どうしてもギャンブル要素が大きいです。どれだけ準備しても、準備していない論題に出会うことも多いので、「無理じゃないか」と思うことも多いです。
でもそれはおそらくみんな思っていることです。みんなが「無理」と思っているのであれば、みんな「微妙」な論文を書いているはずなので、あまり良い論文が書けなくても勝機はあります。
以外と「簡単。できた。やった!」と思う試験は落ちているんですよね。逆に「マジで死んだ」と思っている試験は受かっていることが多いです。
資格の勉強方法~論文対策編~についてはいったん終了です。
このシリーズで利用した「平成28年のプロジェクトマネージャ試験 午後Ⅱ-問2」については以下を参照してください。
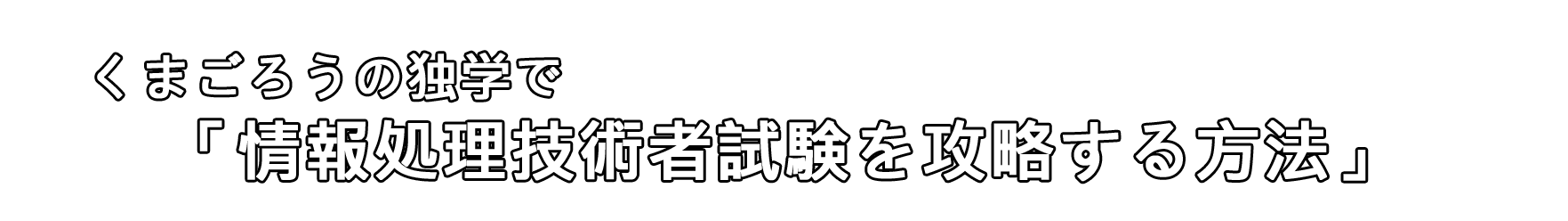







コメント